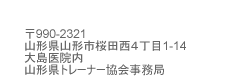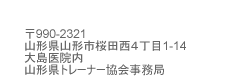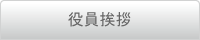 

 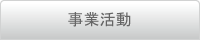
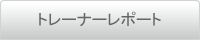
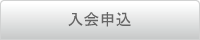
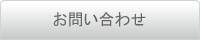
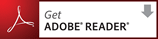
当サイトのリンクページには、一部pdfファイルを使用しています。ご覧いただけない場合は左記アドビリーダーをダウンロードして下さい。 |
 |
■第9回 山形県トレーナー大会の実施 平成22年11月20日(土) 山形テルサ
|
 
|
<第1部 基調講演> 殖田 友子 先生 (帝京大学 准教授)
「競技力向上の栄養学〜”守り”と”攻め”のスポーツ栄養戦略」
・自分にはどういう筋肉が必要なのかを理解することがスタート。
栄養の方針も決めよう!
・食べることの「楽しさ」も大切=食育の基本
・長年の蓄積で身体ができてくる。 肉より魚
・ノートに記録しよう。 よかったこと。目標としたこと。考えたこと。
振り返りが大切。
*「早寝・早起き・朝ごはん」 すべてはここから始まる。
「食うやつが勝つ。寝るやつが育つ。餃子はえらい。」寝ている
間(筋トレ直後)に成長ホルモンがでる。筋トレ前に「おにぎり」、
その後に食事、そして寝る。
餃子の栄養素 豚肉・キャベツ・ニラ・ネギ・しょうが・にんにく
ビタミンB1とそれをパワーアップさせる栄養素。
スポーツ選手が摂るべき栄養量は、母や姉の2倍!
動く分より食べること(小・中学生は成長期…食うやつが勝つ)
「夏こそガッツリ!!めしを食え」練習量が増えるなら、食べる量も
増やせ。 |
<第2部 パネルディスカッション> コーディネーター 山口 喜代美
テーマ アスリート(競技者)の食べ方(食事) 〜山形の現状〜
|
 |
*庄司 秀幸 先生 (山形県立山形中央高野球部監督)
・食事と身体づくり 食事とパフォーマンスの関連性について
甲子園に行って上手くなるチームは24時間のライフマネジメントができ
ている。限られた練習時間と余暇の使い方が大事。
・選手の食事について実際に取り組んでいること
血液検査を通して、栄養指導やケガ防止につなげる。練習前後に補食
を摂るなど生徒自身の栄養管理ができている。
・人間力を身につける
基本的な生活習慣も含めて、野球以外の人間力を身につけていくこと
が大事。
・食事は基本
数年かけ身体を変える。最後の踏ん張りがきく身体づくり。
|
 |
*齋藤 るみ 先生 (県教育庁 スポーツ保健課主査)
・子どもたちへの食育を通して改善が必要だと思われることは、朝食抜
きや好き嫌いによる偏食のこと。コンビニがあって便利な一方、何を食
べるのか選択能力も問われている。
食べ残しの問題もある。食事を作ってくれた人への感謝の気持ちを大
事にする。
・スポーツ栄養に関しては、知っている人が知らない人に教えてあげるこ
とが大事。
・学校栄養士や栄養教諭の先生もスポーツ栄養の知識は必要である。
また、知識と共にメンタルサポートも大事。
|
 |
*中間 紀子 先生(大塚製薬ニュートラシューティカルズ 学術担当)
・中高校生アスリートの食事と身体づくり、食事とパフォーマンスの関連
性については、とにかくよく食べること、それも好き嫌いなく。一流選手
の共通点。
・低レベルのアスリートは、朝食もまともに摂っていない。(エネルギーに
なっていない)朝食は、土壇場での「ここ一番」で力を出させてくれる。
|
 |
*松原 梨香 先生 (パイオニアレッドウィングス 調理師)
・スポーツ食の提供の時に気をつけていることは、手間をかけること、
出すタイミングが大事、嫌いなものがあれば食べやすく(混ぜる・細か
くする)したり工夫をすること。選手とのコミュニケーションも大事。
毎日の積み重ねが選手の身体づくりに反映される。
・選手の食べ方をみて気づくことは、いい選手は「食」への意識が高い。
体重管理もしっかりできる。好き嫌いがある選手は、ケガをしたり、気
分にムラがあったりする。
|
 |
*殖田 友子 先生の まとめ
・食べているものが、どのような栄養につながるのかを考えて食べる。
自分のスポーツにおいてどの部分の身体づくりにプラスになるのか、
などを理解することも大事。
・スポーツ栄養は、自分だけではなく、周りの方との協力や理解が必要
であり、意識の違いが結果の違いに出る。 |